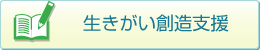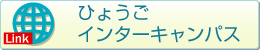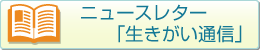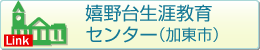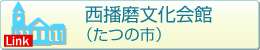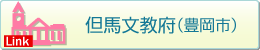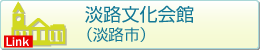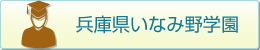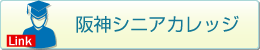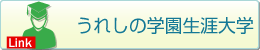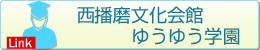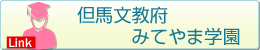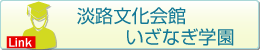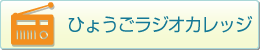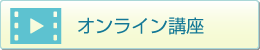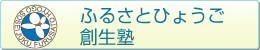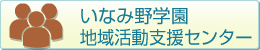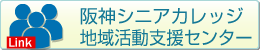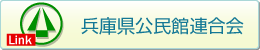令和2年度事業計画
※中項目または事業名の後の( )は実施機関
1 生涯学習・地域づくり活動の総合的推進・支援
(1) 生涯学習に係る情報提供・調査研究の実施
|
事業名 |
事業概要 |
|
①ひょうごインターキャンパス(兵庫県生涯学習の広場)の運営(協会本部) |
・教育機関・民間企業・行政等様々な生涯学習機関と連携し、多彩で幅広い生涯学習情報を提供するウェブサイト「ひょうごインターキャンパス」を運営する。 ・参画機関として登録されていない公民館、生涯学習センター、高齢者大学等に対し、個別に参画を働き掛け、登録の促進を図ります。 |
|
②生涯学習リーダーバンクの運営(協会本部) |
・生涯学習で得た知識・技能を生かし、ボランティア指導者として学習グループ等の活動支援をしようとするふるさとひょうご創生塾卒塾生やいなみ野学園研究生の新たな登録を促進するとともに、その利用促進を図り、学びの社会還元を推進していきます。 |
|
③生涯学習推進アドバイザー派遣事業の実施(協会本部) |
・市町や生涯学習関係機関が抱える課題の解決を支援する生涯学習推進アドバイザー派遣事業を実施します。 |
|
④大学生等との公民館利用など生涯学習に関する調査研究の実施(協会本部) |
・若年層の公民館事業参画を促進するため、大学生等の公民館利用など生涯学習に関する活動実態について、調査研究を実施していきます。
|
|
⑤「新しい生活 活動応援コーナー」(仮称)の開設【新規】(協会本部) |
・講座、資格、施設、イベント等に関するチラシ、パンフレット、冊子等をそろえ、各種の生涯学習情報を提供するとともに、学習計画の立て方、学習グループの運営方法等についての相談に応えるため、設置している「生涯学習情報コーナー」に替えて、新たなライフスタイルにワンストップで対応できる窓口(「新しい生活 活動応援コーナー」(仮称))を新規開設します。 ○現生涯学習情報コーナー(ハーバーランド庁舎6階) 開館日時:月~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)9:00~17:15 電話番号:078-360-9015 |
|
⑥生涯学習情報の収集と提供(嬉野台、但馬、西播磨、淡路) |
・県民の生涯学習を支えるため、生活創造情報プラザにおいて、市町等が発行するイベント等情報刊行物をはじめとした生涯学習に関する情報を収集し、提供します。 ・但馬文庫 青少年及び成人の教養を高め、地域文化の向上を図るため、但馬文庫において図書及び視聴覚資料等を収集・整理し、県民の利用に供することによって、但馬の良さを知ってもらい、ふるさと但馬を愛する心を培うとともにこころ豊かな人づくりに資します。所蔵資料の再整理・ネット等による情報発信を進めるとともに、他の社会教育施設との相互利用など、所蔵資料の活用促進を図ります。 ・淡路文化会館ライブラリー 淡路文化会館が所有する図書、資料、視聴覚資料等を閲覧、貸出に供するとともに、広域ネットワーク上で公開するなどして広く一般の利用に提供します。 |
(2) あらゆる世代の生涯学習を支援する公開講座の実施
|
事業名 |
事業概要 |
|
|
①生涯学習公開講座 |
|
|
|
|
協会本部 |
・現役世代を含むあらゆる世代の生涯学習に対する意識の高揚を図るため、生涯学習公開講座を開催します。 |
|
いなみ野学園 |
・「いなみ野学園特別公開講座」として、政治・経済、芸術・文化、防災等について著名な有識者による講座を広く県民を対象にして開催します。 |
|
|
阪神シニアカレッジ |
・オープンカレッジなどの機会を活用し、カレッジで実際に授業を担当する講師等による公開講座を実施します。 |
|
|
嬉野台生涯教育センター・但馬文教府・西播磨文化会館・淡路文化会館 |
・市町、大学、民間の取組みとも連携しながら、県民ニーズに対応した生涯学習の企画・推進を行い、学習の場の提供を行います。 |
|
② いなみ野学園多世代交流応援プロジェクトの実施
いなみ野学園の休園日の学舎を活用し、学園生と地域の多世代住民がともに学び、交流するイベントや、地域づくりに関する講演会などを実施します。
〔講座・イベント例〕
子育てコーチング講習会、親子陶芸教室、古代鏡・銅鐸作成教室 など
(3) 生活創造活動グループに対する支援
|
事業名 |
事業概要 |
|
|
①生活創造情報プラザ |
・芸術文化、環境、消費生活、健康、福祉等の様々な分野にわたる生涯学習、地域づくり活動等、成熟社会にふさわしい豊かな生活を創造するための県民による主体的な活動(生活創造活動)の拠点施設として運営します。 |
|
|
|
うれしの生活創造プラザ(嬉野台) |
・生活創造活動の促進を図るため生活創造活動グループの活動を支援し、グループ間の相互交流を推進するとともに、うれしの生活創造応援隊によるくらしに関する情報の収集・発信(生活創造しんぶん「ぐぐっと!北播磨」の発行等)を行う。加えて、平成28年10月から設置している展示コーナーにおいては、地域の情報や県民の学習成果の発表の場となるよう各種展示会を開催します。 ・うれしの春のフェスティバル 例年、5月4日に、嬉野台生涯教育センターを広く一般に開放し、芸術・文化・スポーツイベントの実施、地域における活動団体の交流などを行うフェスティバルを開催する。また、HAP体験会の実施など事業の拡大を図ってきており、一層の内容の充実を図ります。 ・生活創造プラザギャラリー センターを活動拠点としているグループや団体の作品を、年間を通じて生活創造プラザに展示し、広く発表する場を提供します。 ・うれしの生活創造プラザ、生活創造応援隊の育成支援 地域に根ざした情報誌を年3回(各3,000部)発行して、北播磨地域の各施設に配布します。 |
|
但馬生活創造情報プラザ(但馬) |
・みてやま朝市 みてやま学園学生や生活創造活動グループ等利用団体の活動を支援し、地域の方々との交流促進を目的とする朝市を開催し、賑わいを創出します。 |
|
|
西播磨生活創造情報プラザ(西播磨) |
・西播磨生活創造活動グループ交流会 生活創造応援隊を中心に企画運営する「西播磨生活創造活動グループ交流会」において、生活創造活動グループの活動の相互交流及び情報交換の場を提供します。 ・西播磨生活創造しんぶん「ネットめばえ」の発行 生活創造応援隊員が地域で活躍されている方々や地域の話題等を「ネットめばえ」で情報を提供し、地域の輪をひろげます。 ・企業協賛広告を募集し、財源の確保も行っていきます。 ・生活創造活動グループの育成支援 活動場所の提供、印刷機の利用などにより、自主グループの活動を支援します。 ・生活創造活動グループの「ボランティア活動情報」をホームページで公開し、利用者のニーズに応じたグループとのマッチングを行います。 |
|
|
淡路生活創造情報プラザ(淡路) |
・生活創造活動グループ交流会 「淡路生活創造情報プラザ」に登録している生活創造活動グループの発表と交流の機会を設け、その活動を広く住民に知って頂くことで、住民の生活創造活動への参加を促すとともに淡路生活創造情報プラザを利用いただく新たな生活創造活動グループを発掘します。 ・「生活創造しんぶん」の発行 地域で行われている生活創造活動や文化的な催しに関する情報を掲載した「生活創造しんぶん」をフルカラーA4判8頁で、毎月発行します。 |
|
(4) 生涯学習関係機関職員研修の実施
地域における学習拠点・活動拠点である公民館等の生涯学習関係機関の職員等を対象とする体系的な研修の機会を提供し、地域課題の解決に必要なファシリテート力、コーディネート力等を養成する研修等により、関係職員等の資質向上を図る。
① 新任社会教育関係職員等研修(協会本部)
社会教育関係職員として、職務を遂行する上で求められる基礎的知識や技能を習得するための研修を実施します。
・開催回数 年1回
・対象者 社会教育・生涯学習関係職員等(経験2年未満程度)
② 社会教育関係職員スキルアップ研修(協会本部)
会議ファシリテーション力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力、広報計画力など社会教育推進に向けた専門的な知識や技能を習得するための研修を実施します。
・開催回数 年4回
・対象者 社会教育・生涯学習関係職員等
③ 社会教育・生涯学習主管課長及び社会教育施設長等研修(協会本部)
社会教育主管課長や公民館長を対象に国・県の施策等社会教育・生涯学習の動向を学ぶとともに研究協議を行う研修を実施します。
・開催回数 年1回
・対象者 社会教育・生涯学習主管課長、公民館長等社会教育施設の長等
(5) ふるさとひょうご創生塾の実施
活力あるふるさと兵庫の実現のため、県政との協働による自主自律の地域づくり活動の拡充を図り、多世代(価値観の異なる青年・壮年・老年)が入塾して新しい地域リーダーを養成するふるさとひょうご創生塾の基本理念・設置目的の達成を目指します。
① ふるさとひょうご創生塾
・県内大学との連携を図るとともに、県、市町、社会福祉協議会等の若手職員や子育てを終えた女性へのPRに努め、多世代の入塾を促進します。
・大学生をはじめとする青年層・壮年層の入塾を促進します。
・地域づくり活動に係る社会的ニーズを的確に反映できるようカリキュラムの随時見直しを行います。
〔塾資格・定員等〕
|
入塾資格 |
地域づくりのための知識を学び、地域づくりのリーダーとして活動することができる者(県内に在住、在勤、在学) |
|
学習年限 |
2年 |
|
授業日等 |
原則として1年次は毎月第2・3土曜日、2年次は第4土曜日の10~16時 |
|
学習場所 |
神戸クリスタルタワー内会議室等 |
|
定 員 |
30名 |
|
経 費 |
受講料(年間)30,000円 |
|
運営体制 |
塾長や学識経験者、実践家による「企画運営委員会」を設置し、時代の流れに即応したテーマを講座に反映します。 |
2 地域社会を支える高齢者の学びの支援
(1)高齢者大学事業の充実
・ 幅広い教養の涵養やクラブ活動を通じた仲間づくりなど、引き続き高齢者の生きがいづくりを支援するとともに、学習成果を地域社会で生かす取組みを強化するなど、高齢者大学事業の充実を図る。
・ いなみ野学園、阪神シニアカレッジ及び各地域高齢者大学は、立地する地域の特色、施設の状況、学生の学習ニーズ等を踏まえそれぞれの個性をより生かした先進的な講座運営等を目指す。
① いなみ野学園
ア いなみ野学園大学講座
高学歴化や価値観の多様化が進むポスト団塊世代のニーズに柔軟かつ機動的に応えるため、平成30年1月の「いなみ野学園カリキュラム検討懇話会からの提言」を踏まえ、見直しを行った学習課程等を、令和元年度入学生から実施したところであり、学年進行により、令和2年度においては、新2年生に実施していくなど、時代に対応したシニアの学びの場を提供します。
〔入学資格・定員等〕
|
入学資格 |
概ね56歳以上の県内在住者で、学習や地域活動に意欲のある者 |
|
|
学習年限 |
4年 |
|
|
授業日等 |
授業日 |
・第1学年=月曜日 ・第2学年=火曜日 ・第3学年=木曜日 ・第4学年=金曜日 |
|
授業時間数等 |
・授業 週1回 ・毎日の授業時間数=90分×2回の講義、実習と園外実習。 1~2年 共通講座20講座・専門講座40講座 3~4年 午前:>共通講座、午後:学科別講座 各30講座 |
|
|
定 員 |
園芸学科・健康づくり学科・文化学科 各100名 陶芸学科 40名 計340名 |
|
|
経 費 |
入学金 6,000円 ・受講料(年間) 50,000円 その他実習費等 |
|
〔講座内容〕
|
講座名 |
学習目標 |
学習内容 |
||
|
共通講座 |
専門講座の基礎的な講座と様々な分野についての見聞を広げ、地域を支え、学び続けるため、「深く兵庫を学び、広く世界を知る」「健やかに生き、安全・安心に暮らす」「生きがいを創り、人間を磨く」に則り、計画的な講義を同一年次の受講生全員が共通して学ぶ。 |
歴史・文化、自然、生き方、人間関係、 |
||
|
専門講座 |
園芸学科 |
園芸に関する知識と技能を修得するとともに、広く農業や環境保全の問題について学ぶことにより、地域に貢献する意識と能力を身につける。 |
園芸植物の栽培基礎、野菜・草花・果樹・樹木その他の園芸知識、園芸に関する時事問題、地域貢献 |
|
|
健康づくり学科 |
こころとからだの調和がとれたより良い生活を実践するモデルとなるとともに、健康づくりを通じて地域に貢献する意識と能力を身につける。 |
からだ・運動(実技・運動概論)、食事・住居・環境、健康・福祉、地域貢献、その他 |
||
|
文化学科 |
文化や歴史、芸術、文学に関する教養を深めるとともに、学びを通じて地域に貢献する意識と能力を養う。 |
ふるさとの地誌、兵庫の偉人、日本の歴史、日本の文学・語学、伝統文化、世界の文化、異文化理解、芸術の世界、表現、旧跡探訪、その他 |
||
|
陶芸学科 |
陶芸に関する基礎的な知識や技能を学び創作するとともに、作品鑑賞を通じた豊かな心の醸成により地域社会に貢献する意識と能力を身につける。 |
陶芸の歴史と鑑賞、作陶、施釉、焼成、その他 |
||
イ いなみ野学園大学院講座
高齢者大学講座等で学んできた知識や技能を掘り下げ、個人や地域の力を再発見することにより、地域での活動をはじめ、地域づくりに役立つさまざまな活動の手法を学びます。
〔入学資格・定員等〕
|
入学資格 |
2年制以上の県・市町立高齢者大学を卒業(見込みを含む)した者 |
|
学習年限 |
2年 |
|
授業日等 |
授業日 第1学年=火曜日 第2学年=金曜日 授業日数 年間30日 |
|
定 員 |
地域づくり研究科 計50名 |
|
経 費 |
入学金6,000円 受講料(年額)50,00円 |
〔講座内容〕
|
コース名 |
学習目標 |
学習内容 |
|
歴史・文化コース |
地域の歴史、兵庫の歴史、地域の文化、日本の文化を極める。 |
日本・諸外国の歴史・文化、地域の歴史・文化、伝統行事・伝統文化、文化遺産、文学、偉人、その他 |
|
健康・福祉コース |
自分たちの健康は自分たちで守る。地域の福祉もみんなで考える。 |
健康・福祉、ボランティアグループの運営、レクリエーション、その他 |
|
環境・地域コース |
現在を知り、人と自然に優しい、子どもたちに残せる環境を考える。 |
環境保全と地域活動、再生可能エネルギー、日本のエネルギー消費、生物多様性、その他 |
|
景観園芸コース |
自然や風土を見つめ直し、豊かな暮らしのあり方を考える。 |
地域の自然・風土、造園・園芸、景観園芸による地域づくり、その他 |
ウ 研究生制度
高齢者大学の卒業生を活用した生涯学習指導者の養成を図るため、いなみ野学園大学院講座修了者を対象に、生涯学習指導者としての研究及び実践活動を行う研究生制度を運営します。
|
対 象 者 |
いなみ野学園大学院修了者 |
|
研究期間 |
5年限度 |
|
内 容 |
研究計画書の提出及び研究期間末に成果報告を提出します。 |
|
研究機会 |
年15回(公開講座・ゼミなどの登園日数>) |
|
経 費 |
負担金 (年間)25,000円 |
エ 聴講生制度
いなみ野学園高齢者大学の講座の一部を公開し、地域づくりについて学ぶきっかけづくりや実践活動の充実につなげていきます。
さらに「人生100年時代」に対して退職後の生き方を考える世代(退職準備世代)に学びの場を提供し、就業・介護等の事情から高齢者大学への入学が困難な層にも学習の機会を提供します。
・受講料(1講座あたり) 学生・卒業生1,300円、一般1,500円
オ 地域活動支援センター
卒業生等へのボランティア情報提供やボランティア団体の創設・運営等を支援する「地域活動支援センター」を運営し、県高齢者大学卒業生等が行う地域づくり活動を促進します。
また地域づくり活動グループの活動発表の場やシニアの地域づくり活動の現状を考える機会として、フォーラムなどの行事を開催します。
カ 学園運営等サポーター 高齢者大学の講座運営等を支援する高齢者大学等運営サポーターを募集、登録し、高齢者大学卒業生等の学習成果を活かしていくとともに、高齢者大学等の活性化を図っていきます。 〔学園運営サポーター〕 種 別 内 容 (講座等)運営サポーター(8名) 大学院や大学の講座における円滑な講座運営のための講座補助業務を行います。〔採用対象〕研究生 陶芸学科運営サポーター(1名) 学科テキストの作成や配布資料の作成、または園外学習や出前教室等地域活動の企画・運営を行います。〔採用対象〕卒業生 地域活動支援センター運営サポーター (3名) 地域貢献アドバイザー〔採用対象〕学識者 地域活動インストラクター〔採用対象〕研究生 ラジオ番組事業サポーター(25名程度) ラジオ関西と共同で制作するシニア向けの情報提供番組「いなみ野シニアの元気ニュース!」の制作に参加協力し、取材活動や放送業務を補助します。〔採用対象〕大学講座学生等 学園広報サポーター CATV番組や広報ビデオ、名刺の制作などを行います 公開講座運営サポーター (6名) 公開講座・しごと活躍講座の運営等を行います。 みどりのサポーター いなみ野学園敷地内の庭木や草花の植栽管理活動を行う「みどりのサポーター」を募集・登録し、「いなみ野ガーデニングの日」に学園敷地内の植栽管理活動を行っていただきます。 ・対 象 者 いなみ野学園卒業生 高齢者園芸センターサポーター(10名程度) 作物の生産販売を行うサポーターを設置し、卒業生の学びを生かす実践農場として活用していきます。 ・場 所 高齢者園芸センター キ しごと活躍講座【拡充】 平日の午後やいなみ野学園の休園日などの学舎を活用し、生活支援分野等において、有償ボランティアとして活躍するために必要な基礎知識を習得するための講座を開設します。 令和2年度においては、令和元年度受講生に対する振り返りやブラッシュアップを図る「フォローアップ研修会」の開催や、いなみ野が県に加えて県内3か所でも実施し、開催場所の拡大も図ります。 〔講座例〕 看護補助者養成講座、剪定の基本講座、保育支援講習会、 日本語講師ボランティア養成講座、生活支援(施設・訪問介護)講習、 剪定スタッフ講習 ク いなみ野学園運営の見直し検討【新規】 いなみ野学園は、高齢者大学の先進モデルとして、高齢者の生涯学習、地域貢献活動の推進の役割を担ってきました。そして、創立50周年を機に学習内容等を見直し、令和元年度入学生から専門講座の充実を図るとともに、在籍年限や年齢制限の緩和、学園の広報活動の強化を図りましたが、依然、高齢者大学を取り巻く環境は厳しく、入学者が定員を充足できない状況が続いています。 そこで、学園ニーズに即した学園運営の見直しを行うため、「いなみ野学園運営検討委員会」(仮称)を設けるほか、魅力ある学科運営による学園生増加対策や事務事業の見直しによる支出削減対策の検討を行い、学園経営の健全化に取り組みます。 ② 阪神シニアカレッジ 令和元年度から、4か所に分散していた学習室を統合し、新学(宝塚市)での講座を開始しました。これを契機に、学科の枠を超えた学生交流や、多様な意見・考え方に触れる機会の増を図るとともに、学生の地域活動の拡充を支援します。 ア 阪神シニアカレッジ大学講座 高齢者が生涯学習を通して教養をより高めるとともに、「生涯現役」として創造的に生きるための多彩なプログラムを提供します。
〔入学資格・定員等〕 入学資格 生涯学習に関心のある56歳以上の神戸・阪神地域在住者 学習年限 4年 授業日等 授業 週2回(共通講座1日、専門講座日) 定 員 園芸学科・健康学科・国際理解学科 各50名 計150名 経 費 入学金6,000円 受講料(年間)50,000円 〔講座内容〕 区分 概要 主な学習内容 共通講座 ○園芸、健康、国際理解の3学科に共通する分野 ・現代社会、芸術・文化、生命の豊かさなど、人文・社会科学関係 専門講座 園芸学科 ○専門講師による高度な実演・実習 ・園芸界の第一線で活躍する専門講師が理論と実演実習を織り交ぜて指導
健康学科 ○病気についての正しい知識と理解 ・内科学、外科学を医学の立場から学習
国際理解学科 ○世界の諸地域の理解 ・世界諸地域の特性や課題を多面的に捉え、その多様性や価値観などを学習
イ 阪神ひと・まち創造講座 地域社会等での人間関係のあり方、コミュニケーションのあり方を改めて学び、あわせて阪神地域の歴史・文化・産業・自然などの魅力や課題等を再認識することで、地域への愛着をもってコミュニティ活動等意欲の醸成とコミュニティの活性化を目指します。 〔入学資格・定員等〕 入学資格 生涯学習等に関心のある56歳以上の神戸・阪神地域在住者 学習年限 2年 授業日等 授 業 日 第1学年=火曜日 第2学年=木曜日 定 員 30名 経 費 入学金6,000円 受講料(年間)25,000円 〔講座内容〕 概要 主な学習内容 ○仲間をつくる ・コミュニケーション能力のスキルアップとさらなる進化 ・地域の自然や歴史、人物や文化、文芸や産業などの魅力を再発見し、地域貢献のスキルアップ ・NPO法人やボランティアグループからコミュニティビジネス等のノウハウを学習 ・地域貢献を実践するための基本理念や企画を学習 ウ 聴講生制度 高齢者大学の講座の一部を公開し、カレッジライフの楽しさを体験していただき、募集要項を送付するなど学生の確保につなげていきます。 ・受講料(1講座あたり) 学生・卒業生1,300円、一般1,500円 エ 地域活動支援センター 卒業生等へのボランティア情報提供やボランティア団体の創設・運営等を支援する「地域活動支援センター」を運営し、県高齢者大学卒業生等が行う地域づくり活動を促進します。 ・主な機能 グループ登録やマッチング等の地域での実践活動のきっかけづくり。 地域活動の企画・運営に関する相談、研修会、講演会の開催、広報 紙の発行など活動成果の情報発信 オ 学舎統合による魅力の向上 学舎統合による学生間の相互交流や活動の活性化を受け、高齢者による豊かな地域創生の拠点としての魅力を広く発信し、「新生」阪神シニアカレッジをアピールしていきます。 ③ 嬉野台生涯教育センター ア うれしの学園生涯大学(4年制大学講座) 生涯学習の一環として、高齢者に総合的・体系的な学習機会を提供し、生きがいある充実した生活基盤を確立することを目指すと共に、地域活動の実践者を養成することにより、高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進に寄与することを目的とします。 〔入学資格・定員等〕 入学資格 概ね60歳以上の原則東播磨・北播磨地域在住で、地域での活動に関心や意欲のある方。 学習年限 4年 授業日等 開設期間 令和2年4月14日~令和3年3月2日(全20日間) 定 員 60名 経 費 受講料(年間)12,500円 〔講座内容〕 講座区分 学習目標 学習内容 共通講座 地域活動実践上の基礎となる知識やスキル、ノウハウを習得します。 仲間づくりやコミュニケーション、地域づくりの基礎に関する学習、学年別宿泊研修(世代間交流や自主企画講座など)、学園祭(舞台発表、作品展、記念講演、スポーツ大会)、実践発表会、入学式(記念講演)、修了証書授与式等を行います。 専門講座 地域活動実践を行うための背景となる現代的課題や地域への認識を深めます。 健康の増進、コミュニケーション、運動、病気の予防、社会福祉、国際理解、男女共同参画、次世代育成支援、環境問題、消費者問題、郷土文化歴史、地域産業、時事問題、防災等について学びます。 イ うれしの学園生涯大学大学院講座 高齢者大学講座での学習を基礎として生かし、地域の課題を専門的・実践的に学び知識や技能のステップアップを図るとともに、スキルアップ自主企画講座の柔軟な設定やそれに伴う4年制大学講座の受講など自由と自主性を尊重したカリキュラムにさらに取り組み、主体的に地域社会に関わる意欲を持った地域づくり活動の担い手を養成していきます。 〔入学資格・定員等〕 入学資格 概ね60歳以上の原則東播磨・北播磨地域在住で、地域での活動に関心や意欲のある方。 学習年限 2年 授業日等 開設期間 令和2年4月14日~令和3年3月2日(全22日間) 定 員 30名 経 費 受講料(年間)12,500円 〔講座内容〕 区分 学習目標 学習内容 1年次 「学びと実践の一体化をめざして」をテーマに、地域を知り、地域における課題に対してより実践的・主体的に取り組むための知識や技能の習得を行います。 地域活動実践の基礎的知識や技能、地域の歴史・文化・自然・産業などの地域の魅力を学ぶと共に、興味関心に基づいて活動テーマを探し、グループ毎に地域活動実践を行います。 2年次 主体的な地域活動を実践し、発表を行い、修了後も、学びの成果を地域社会へ還元し、無理なく楽しく地域実践活動を続けていくことをめざします。 1年次の学習をもとに、テーマに関する専門的事項を学ぶとともに、グループ毎に調査・研究・体験等の地域活動を実践します。 ④ 但馬文教府 ア みてやま学園(4年制大学講座) 豊かで生きがいのある生活を送るために、自己の健康づくりや地域づくり活動の実践力を培うなどの生涯学習の機会を提供するとともに、ここでの学びを通して長寿社会を担う地域活動の実践者を養成し、生きがいづくりや社会参加の推進に寄与することを目的とします。 〔入学資格・定員等〕 入学資格 概ね60歳以上の但馬地域在住者 学習年限 4年 授業日等 開設期間 令和2年4月10日~令和3年3月5日(全26日間) 定 員 60名 経 費 受講料(年間)12,500円 〔講座内容〕 講座区分 学習目標 学習内容 共通講座 変貌する社会の課題に柔軟に対応するための教養、知識を習得します。 全5回 専門講座 健康づくりコース 高齢者の生きがいづくり及び地域の特性や課題に対応した地域活動についての専門的知識、実践力を養成します。 ※左の6コースから2コース選択 7回×2コース=14回 ・リズム体操やツゥゲットボール等、楽しく体を動かす。 但馬の文化コース ・但馬の歴史、文化、芸能、人物等について学ぶ。 但馬の自然・産業コース ・但馬の自然やそれを生かした産業について学ぶ。 麦わら細工コース ・城崎に伝わる伝統工芸、麦わら細工の作品づくりを学ぶ。 書道コース ・書道の基本を学び、楷書・行書の作品づくりを学ぶ。 パソコンコース ・ワードやエクセルの基本技能について学ぶ。 イ みてやま学園大学院(地域活動実践講座) 4年制大学講座での学習をもとに、実践的な社会参加活動について学習することにより、地域づくり活動などに主体的に取り組む意欲をさらに醸成するとともに、実践力を習得することで、地域づくり活動等の実践者を養成します。 〔入学資格・定員等〕 入学資格 但馬地域在住で県立4年制高齢者大学講座又は市町立の高齢者大学等を修了した者 地域活動に意欲のある概ね60歳以上の者 学習年限 2年 授業日等 開設期間 令和2年4月10日~令和3年3月5日(全21日間) 開 講 日 原則として月2回隔週火曜日 定 員 30名 経 費 受講料(年間)12,500円 〔講座内容〕 区分 学習目標 学習内容 1年次 高齢者大学等での学習をもとに、実践的な社会参加活動に必要な基礎的な知識や技能を習得します。 基礎講座 2年次 グループ別実践活動を充実するとともに、実践的な社会参加活動への意欲を高めます。 応用講座 ⑤ 西播磨文化会館 ア ゆうゆう学園(4年制大学講座)) 生涯学習の一環として、高齢者が豊かな生きがいのある生活を送るために必要な教養と、地域づくり活動に役立つ専門知識や技能を身につけられるよう、総合的・体系的な学習の場を提供し、高齢者の生きがいづくりや地域の活性化を推進します。 〔入学資格・定員等〕 入学資格 概ね60歳以上の中播磨・西播磨地域在住者 学習年限 4年 授業日等 開設期間 令和2年4月24日~令和3年3月5日(全27日間) 定 員 60名 経 費 受講料(年間)12,500<円 〔講座内容〕 講座区分 学習目標 学習内容 共通講座 (教養講座) 変貌する社会の課題に柔軟に対応するための教養、知識を習得します。 ・高齢者の役割と生き方、社会の現状認識、地域の将来、地域づくり活動、人権・道徳、政治・経済、歴史・文化、環境、その他 専門講座 環境創造 高齢者の生きがいづくり及び地域の特性や課題に対応した地域活動についての専門的知識、実践力を養成します。 ・自然環境や社会環境の現状とあるべき将来について学び、健やかで安全に暮らせる環境づくりを実践するための専門的知識や実践力を身につける。 健康福祉 ・心身の健康や福祉について学び、地域活動やボランティア活動に必要な専門的知識や実践力を身につける。 地域文化 ・地域文化や歴史等について学び、まちづくりや社会教育活動、地域間・世代間交流など、地域活動に貢献できる専門的知識や実践力を身につける。 学年別講座 自主性、企画力、実践力の養成 ・学年に応じた学習内容を自主企画し実践します。 イ ゆうゆう学園大学院(地域活動実践講座)
4年制講座等での学習をもとに、実践的な社会参加活動について学習することにより、地域における課題に対して、より主体的、実践的、専門的に取り組むことができる人材を育成し、地域発展に寄与できる実践者としての資質を養います。 〔入学資格・定員等〕 入学資格 中播磨・西播磨地域在住で4年制高齢者大学講座又は市町立の高齢者大学等を修了した者 学習年限 2年 授業日等 開設期間 令和2年4月24日~令和3年3月5日(全22日間) 定 員 30名 経 費 受講料(年間)12,500円 〔講座内容〕 区分 学習目標 学習内容 1年次 高齢者大学講座等での学習をもとに、実践的な社会参加活動について総合的・体系的、かつ実践的に学習することにより、地域づくり活動などへの主体的な取組意欲を醸成し、実践者としての資質を養います。 ・基礎講座 ・現地体験学習(学外研修等) ・自主企画講座 2年次 1年間の学びの後、取組の成果を地域社会に還元することをめざし、専門コースごとに主体的・継続的な地域活動について調査・研究・実践を行います。 ・応用講座 ・現地体験学習(学外研修等) ・実践報告会 ⑥ 淡路文化会館 ア いざなぎ学園(4年制大学講座)) 高齢者に学習年限4年で総合的、体系的な学習の機会を提供し、高齢者が生きがいある充実した生活基盤を確立し、地域の実践者としての素養を身につけることを支援します。 〔入学資格・定員等〕 入学資格 概ね60歳以上の県内在住者 学習年限 4年 授業日等 開設期間 令和2年4月22日~令和3年3月10日(全26回) 定 員 60名 経 費 受講料(年間)12,500円 〔講座内容〕 講座区分 学習目標 学習内容 共通講座 充実した生活基盤の確立や社会変化への対応のために必要な基礎的素養を身につけます。 ・郷土文化、生活、芸術、時事、健康など 専門講座 歴史文化 自己の興味関心を伸長します。 ・淡路、兵庫、日本に関する歴史文化 健康環境 ・健康、福祉、医療、環境(エコ)、エネルギー 実技実習講座 幅広い知識と技能を身につけるきっかけとするとともに、新たなことにチャレンジする意欲を高めます。 ・食、ものづくり、健康運動から選択する体験学習 学年別講座 学年で話し合い、テーマを決めて計画、実践、ふりかえりをすることにより段階的に地域学習・地域実践の能力を高めていきます。 ・安全講習 ・交流学習 ・テーマ学習 特別講座 国生みの島元気っ子フェスティバル、 イ いざなぎ学園大学院(地域活動実践講座) 高齢者大学講座を修了した者に、学習年限2年で社会参加活動に係る総合的、体系的かつ実践的な学習機会を提供し、高齢者が地域づくり活動の実践者となることを支援します。 〔入学資格・定員等〕 入学資格 県立4年制若しくは市町立の高齢者大学等を修了し、又は淡路文化会館長が地域活動に意欲があると認めた概ね60歳以上の県内在住者 学習年限 2年 授業日等 開設期間 令和2年4月22日~令和3年3月10日(全20日間) 定 員 30名 経 費 受講料(年間)12,500円 〔講座内容〕 区分 学習目標 学 習 内 容 1 年 次 地域実践活動、地域の歴史・文化やものづくりに関する基礎的・基本的な知識を習得します。 ・基礎講座 2 年 次 1年次に学んだことを活かし、地域実践活動等を行います。 ・応用講座
(2) 高齢者放送大学事業の充実
ア 高齢者放送大学(ひょうごラジオカレッジ) 著名な講師陣により発信する質の高いラジオ講座を運営し、幅広く県民に生涯学習の機会を提供するとともに、中央・地方スクーリング等を通じた学友との交流の場の提供など、ラジオカレッジの魅力を積極的に発信し、受講生の拡大を図っていきます。 〔入学資格・定員等〕 入学資格 本科生:兵庫県内に在住する満50歳以上の者 学習年限 本科生:1年 ※聴講生、生涯聴講生は1年ごとに更新します。 定 員 本科生:500名 ※聴講生、生涯聴講生は定員を設けません。 経 費 本科生 6,000円 聴講生・生涯聴講生 5,000円 自主活動 県内各地にラジオカレッジ友の会が自主的に結成され、現在28の友の会が活動中です。 〔講座内容〕 区分 運営方針等 学習方法等 ラジオ講座 ・毎週土曜日午前7時から30分間のラジオ講座(ラジオ関西558・但馬地区は1395kHz)を放送します。 ・聴講後、講座の感想文をはがき(またはメール)で提出します。 ・本科生は、月1回程度往復はがきで感想文を提出し、返信用はがきでラジオカレッジ講師から個々に助言します。 ・講義の概要や学生の感想文などを掲載したテキストを毎月1回、増刊号、特集号を年間各1回発行(郵送)します。 スクーリング及び研修 ・学生相互あるいは学生と講師・職員との交流を深めるため、スクーリング、研修旅行、春のつどい、文芸祭を行います。 ・中央スクーリング(年2回) ・地方スクーリング(各年1回) ・研修旅行(県内 年1回1日) ・春のつどい、文芸祭 イ ラジオカレッジサポーター テキスト等の編集や発送に関すること、行事開催に関することなど、ラジオカレッジ運営を支援する「ラジオカレッジサポーター」を募集・登録し、各種事業にスタッフとして参加していただきます。 ・対 象 者 ラジオカレッジ学生 ・募集人員 20名 ・活動日数 年20回程度 (3) 高齢者の交流・健康づくり活動の広域的展開・場の提供 ツゥゲットボール等のシニアニュースポーツの普及、全国健康福祉祭(ねんりんピック)への選手派遣を行い、高齢者の交流・健康づくり活動を広域的に展開していきます。 ① シニアニュースポーツ グラウンド・ゴルフをはじめとするシニアニュースポーツの普及促進を図り、当協会が開発したツゥゲットボールの全県大会を開催します。 ツゥゲットボール全県大会(予定) ・ 日 時 令和2年11月 ・ 参加者 160名(32チーム) ② 全国健康福祉祭(ねんりんピック) 全国の高齢者がスポーツ等を通じて交流を深める全国健康福祉祭(ねんりんピック)に兵庫県選手団を派遣します。 ねんりんピック岐阜2020 ・ 会 期 令和2年10月31日(土)~11月3日(火) ・ 選手団 170名程度 ③ 兵庫県高齢者学習研究協議会【休止】 学ぶ高齢者のつどいの開催や県内の高齢者大学・高齢者教室による連携事業や研修事業等を実施してきました兵庫県高齢者学習研究協議会(事務局:生きがい創造協会)について、その所要経費を負担することが、当協会において困難となったことから、各ブロックにおいて今後も実施することを決定した事業を除いて、当分の間、活動を休止することとします。 3 未来を担う青少年の育成 (1) 生きる力を育む体験教育の実施 ① 嬉野台生涯教育センター 長年にわたり野外活動等による体験教育に取り組んできた嬉野台生涯教育センターを体験学習・野外活動を先導する拠点として位置付け、野外活動学習をはじめとする青少年等に対する体験学習の充実を図り、青少年等の生きる力を育んでいいきます。 ア ひょうご冒険教育(HAP) 県下で唯一の施設の体験による冒険活動を通じて、こころ豊かでたくましい人間を育成することを目指し、信頼や協調性を高める「チームづくり」の機会を提供します。 ・活動回数 年9回程度(5月~2月の各1~3日間) ・対 象 者 社会教育、野外教育、学校教育、生涯学習、社員教育等の関係者 イ 野外活動指導者養成講座 野外活動の基本的な知識・技能を習得するとともに、指導者として必要な資質を身につける機会を提供し、野外活動指導者としての人材を育成します。 ・活動回数 年1回 ・対 象 者 野外活動に関心のある者 ウ 全県野外活動フォーラム 県内の野外活動関係者が一堂に会し、これからの野外活動指導者に必要な資質や在り方についての研修を行うとともにネットワークの構築を図ります。 ・活動回数 年1回(12月に1日間) エ うれしの台ユースセミナー 野外等における豊かな体験活動を通じて、子どもたちに感動や達成感、充実感を味あわせるとともに、集団の中での自律心、規範意識を育成することを通じて「たくましいひょうごっ子」を育成する機会を提供します。 ・開 設 夏(7~8月)に9コース、秋に1コース、冬に3コース、春に1コース ・対象者 小学生・中学生・高校生 ・定 員 各コース30~50名(全555名程度) ・受講料 一人12,000円~25,000円程度 オ ひょうご・ロシアハバロフスク少年少女交流事業 本県の少年少女が、ロシアハバロフスク地方を訪れ(隔年で相互訪問)、交流活動やホームビジット等を通して、国際理解教育や環境学習を推進します。 ・時期等 7~8月に7泊8日で訪問 ・訪問団 生徒12名、引率者4名 計16名(H30年度実績) (県教育委員会社会教育課からの受託事業) カ 学校の学習活動(自然学校、トライやる・ウィーク) 各学校の児童生徒にとって充実した学習活動となるよう、安全面・衛生面等に配慮したプログラムづくりや集団での学びのサポートをします。 ② 但馬文教府 ア 小・中学生作文・詩集「但馬の子ども」の発行 小・中学生から作文、詩を募集し、優秀作品を「但馬の子ども」に掲載します。 ・生活部門:作文、詩 環境部門:作文 ・応募期間:令和2年9月~10月 ・対象者:但馬地域の小・中学生 イ 科学する但馬の子ども作品展、研究集録の発行 豊かな但馬の自然環境の中で生活している児童生徒の科学する心の育成を支援するとともに、自然の事物・現象について理解を深め、科学的思考力を養い、自らの力で探求する喜びを体験し、発表することにより子どもの生きる力を育むことを趣旨として作品展を開催し、優秀作品を掲載した研究集録を発行します。 ・作品展:令和2年9月11日(金)~22日(火・祝) ・研究集録の発行:令和3年3月 ・対象者:但馬地域の小・中学生 ウ 科学チャレンジin但馬文教府 理科教育に関して文教府が培ってきた先導的取組みやネットワークを活かし、幅広い団体、教育機関等との連携により、未来の但馬の担い手や世界レベルで活躍する子どもたちを育成します。 ・日 時 令和2年9月27日(日) ・参加者 小・中学生 エ 多世代ふれあい交流事業 幼児や子育てする親等を対象に、県関係機関、生活創造グループ、教育機関等の参画により遊び体験や育児指導等の親子イベントを通じて文教府の周知及び利用促進を図ります。 ・日 時 令和2年6月 ・参加者 未就学児・小学生とその親 オ 文教府ジュニア陸上教室 体育関係者とのネットワークを活かし、子ども達を対象に全国トップレベルのアスリートから特別指導を受けることにより、スポーツへの興味を深め、地域のスポーツのさらなる振興を図ります。 ・日 時 令和2年8月 ・参加者 小・中学生 カ 創作活動体験教室 3つの創作コースを設けて、但馬地域の芸術家により子どもたちに分かりやすくポイントを伝えながら美術作品の創作ができる体験教室を開催し、子どもたちの芸術活動を推進します。 ・日 時 令和2年8月 ・参加者 小・中学生 ③ 西播磨文化会館 ア 大人も子どもも楽しめる「文化体験教室」【新規】 地域のグループ・団体等と連携して、子どもも大人も様々な文化活動を体験しながら、表現力や想像力を養うワークショップを実施します。 ・実施日:令和2年7月25・26日(土・日) ・実施場所:西播磨文化会館 イ プレーパークへの支援 「子どもの遊び場を考える会赤とんぼ」の活動場所として敷地内を活用。プレーパーク赤とんぼの開催を支援するなど、様々なイベントを通して若い世代との交流を図ります。 ・活動日:原則隔週土曜日(通年) ・実施場所:西播磨文化会館 ④ 淡路文化会館 ア 国生みの島元気っ子フェスティバル 淡路地域で活動する個人や団体が、子どもの健全育成を目的とした様々なプログラムを出展し、こころ豊かで健やかな子どもの育成とともに、豊かなコミュニティ社会の実現を図ります。 ・実施日:令和2年10月4日(日)〈予定〉 ・実施場所:淡路文化会館 ・出展予定:手作り教室、地場産業体験、遊び・ゲーム等のブース、子どもたちの活動成果の舞台・展示発表 など イ 夏休みサイエンス体験広場 淡路島内の中学生・高校生による、小学生等を対象とした夏休みの自由研究や工作のヒントになる楽しい科学の実験やものづくり体験を通じて、子どもたちの科学に対する興味や関心を高めます。 ・実施日:令和2年8月16日(日)〈予定〉 ・実施場所:淡路文化会館 ・出展ブース:「力・運動・光・電気の科学」、「物質の性質と変化の科学」、「生き物の科学」、「宇宙・天文・地球の科学」 など (2) ふるさと意識の醸成
地域の特色を生かした事業を展開し、青少年のふるさと意識の醸成を図っていきます。 ① ふるさと北播磨発見!事業(嬉野台) 北播磨の歴史や文化を再認識し、地域の魅力を発見するため、講座やフィールドワークを開催します。 ・ふるさと北播磨発見!講座(フィールドワーク) ② 小・中学生作文・詩集「但馬の子ども」の発行(但馬)【再掲】 ③ 大人も子どもも楽しめる「文化体験教室」(西播磨)【再掲】 ④ 国生みの島元気っ子フェスティバル(淡路)【再掲】 4 生涯学習に関わる多様な主体との連携・交流
生涯学習や地域づくり活動に対する多彩な県民ニーズに応えるため、多様な生涯学習関係機関、活動団体等とのネットワーク化や連携を進めます。 (1) 大学等学校教育機関との連携
① 兵庫大学、兵庫教育大学等との連携(協会本部、いなみ野)
兵庫大学・兵庫大学短期大学部、兵庫教育大学等との連携により、生涯学習講座の開設、学校施設の相互利用等を実施します。 ② 甲子園大学との連携(阪神)
健康学科のグループ学習の一環として、甲子園大学と連携した講座を組み入れ、〝老若交流〟講座を開催します。 ③ 兵庫教育大学との連携による生涯学習指導者育成研修(嬉野台)
青少年の体験活動や野外活動に関する基本的な理論と実技を修得する教育実習(フレンドシップ実習:兵庫教育大学における科目)を実施します。 ・対象者 兵庫教育大学教育実習生(2年生) ④ 地域の学校教育機関との連携(嬉野台)
うれしの学園生涯大学の講座の一環として兵庫教育大学、県立社高等学校、市立米田小学校、米田こども園等と連携した世代間交流事業を実施し、多世代交流の促進を図ります。 ⑤ 豊岡短期大学との連携(但馬)
豊岡短期大学との連携協定に基づき、講座開設の実施を通して一層の強化を図ります。具体的には、介護制度の概要や子育て等をテーマに、同大学において学生との合同授業やグループ討議などを実施するとともに、文教府のみてやま親子ふれあいフェスタに参加し子ども向け講座を開設するなど、更なる交流を深めていきます。 ⑥ 県立龍野北高等学校との連携(西播磨)
平成23年からの県立龍野北高等学校との連携協定に基づき、互いの持つ資源の有効活用を通じて、高校生と高齢者大学生との意見交換会や看護・介護体験講座、高校生による森づくりなど様々な連携事業を実施します。 ⑦ 地域の学校教育機関との連携(淡路)
いざなぎ学園の講座の一環として、関西看護医療大学、関西総合リハビリテーション専門学校、淡路市立多賀小学校等と連携した世代間交流事業を実施し、多世代交流の促進を図ります。 ⑧ 公益財団法人兵庫県青少年本部山の学校との連携(いなみ野・嬉野台)
山の学校生徒による施設内の倒伐木のほか、交流事業に取り組みます。 (2) 公民館等市町関係機関との連携
公民館が主催する生涯学習講座等の講師の紹介、生涯学習推進アドバイザーやいなみ野学園研究生の派遣などにより、市町の生涯学習事業を支援していきます。 (3) 博物館等社会教育機関との連携
兵庫陶芸美術館及び県立考古博物館との連携により、高齢者大学への講師派遣、各施設の実施事業への積極的な参加等を実施します。 (4) 自治会等各種地域団体との連携
地域学校協働本部が実施する地域学校協働活動(見守り等学校支援活動、放課後子ども教室等)への高齢者大学学生、OB等の参加を促進します。 ①プレーパークへの支援(西播磨)【再掲】 (5) 高齢者大学等関係組織との連携 ① 同窓研修会との連携(いなみ野) 同窓研修会を高齢者大学卒業生の生涯学習機関と位置づけ、講師としての研究生等の紹介を通じて研修活動の充実に協力していきます。あわせて、協会の協働先として、事業実施に協力を求めることとし、「子育て応援事業」の共同実施を働き掛けていきます。 ② ラジオカレッジ友の会(放送大) 高齢者放送大学の「ラジカレ応援団」ともいえる友の会の活性化を図るため、友の会の組織率向上や広報誌発行の継続、運営などに関する課題を代表者会議の中で検討していきます。また、地方スクーリングの機会を通じて、各友の会の会員と職員との意見交換会の実施を働きかけるなど、支援協力を行います。 ③ 阪神シニアカレッジ同窓会との連携(阪神) 新学舎移転に伴い同窓会室を新たに設け、その自主的な活動を支援するほか、同窓会への加入促進・カレッジ学生募集に関する相互協力や、同窓会の自主事業「マイスター講座」で講演する講師の紹介など、相互に連携しながら事業を推進しています。 ④ うれしの友の会との連携(嬉野台) センターに集うすべての人々をつなぐ「うれしの友の会」と連携して、年間100回を超える様々な楽しい体験や交流をしながら、参加者相互の心の交流を図り、こころ豊かな場を創造していきます。 ⑤ みてやま学園学生自治会・同窓会との連携(但馬) みてやま学園学生自治会及び同窓会との連携により地域実践活動講座を実施し、花の定植や清掃活動など文教府周辺道路等の環境美化活動に取り組んでいきます。 ⑥ 但馬高齢者生きがい創造学院との連携(但馬) 但馬高齢者生きがい創造学院との連携を進め、互いの学園祭で交流を深めるなど高齢者の生活創造活動を支援していきます。 ⑦ ゆうゆう学園学生自治会・同窓会との連携(西播磨) 学生自治会・同窓会が連携し、研修会やクラブ活動への参加など様々な交流をしながら、地域におけるボランティア活動等の地域づくり活動の促進へつなげていきます。 ⑧ いざなぎ学園学生自治会との連携(淡路) いざなぎ学園学生自治会の運営に協力し、学園学生相互の親睦を深めることに寄与するとともに、自治会が行う施設内、施設周辺等の清掃その他の環境美化活動を支援することで、いななぎ学園の学習環境の向上を図っていきます。 ⑨ 塾友会等OB会との連携(創生塾) 塾友会等OB会との連携により、卒塾生の地域づくり活動の促進を図ります。 (6) 広域ネットワーク組織との連携 兵庫県公民館連合会等の県域ネットワーク組織との連携を強化するとともに全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会等の全国ネットワーク組織や関西圏・首都圏シニア大学校等の県域を越えたネットワーク組織との連携を強化していきます。 ① 兵庫県公民館連合会との連携 兵庫県公民館連合会との連携において、社会教育関係職員等研修や生涯学習関係調査研究の共同実施を引き続き行い、兵庫県公民館連合会との連携を強化していきます。 ② 全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会との連携(協会本部) 高齢者の生きがいづくり・健康づくりを推進し、地域の支え手となる高齢者を育む活動に取り組む全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会が主催する会議・研修会に参加し、推進機構相互の情報交換や事業推進の協議を行います。 ③ 関西圏・首都圏シニア大学校交流事業(協会本部、いなみ野) 関西圏・首都圏の高齢者大学の運営者・学生・卒業生等に呼びかけ、互いに知識を深め、交流の輪を広げることを目的として実施している当該事業を兵庫県で実施します。(開催地:姫路市) ④ 県内文化施設との連携(あいカード)(全施設) 県内の美術館、博物館等の文化施設における県高齢者大学等学生を対象とする割引利用制度(あいカードの提示による割引)により、学生の学習ニーズに対応するとともに、文化施設の利用促進を図っていきます。 (7) NPO、社会福祉協議会等地域活動団体との連携 ボランティア活動の場の提供、実践体験講座の支援等に取り組むボランティアセンターを運営する市町社会福祉協議会、NPOを育成する中間支援団体等との連携を進めていきます。 (8) 各施設の魅力を生かした地域住民との交流 ① 施設の魅力を活かした地域住民との交流(いなみ野) ・学園の魅力ある資源を活かした陶芸および園芸の地域開放型講座 ② 北播磨地域ふれあい事業(仮称)(嬉野台)【新規】 ・当センターにある野外活動施設(HAP施設を含む)での野外活動体験を通して、北播磨地域内外の人達の交流を深めるとともに、地域へ出向き、「仲間づくり」講座(出前講座)を実施することで、地域の活性化を図ります。 (ア) うれしの地域ふれあいDAY(対象:地域住民等) (イ) うれしの地域ふれあいDAYキャンプ(対象:地域住民等) (ウ) うれしのふれあいアカデミー(対象:地域住民・教育関係者等) (エ) うれしのふれあい地域講座(対象:地域住民等) 5 地域団体等の参画と協働による地域文化活動の支援 文化会館等で展開してきた地域文化活動の振興、地域文化活動団体への支援を更に強化するなど、地域団体等の参画と協働による地域づくりを推進し、青少年の感性(想像力、表現力等)を育むとともに、住民のふるさと意識の醸成や居場所・交流の場づくりなどを進め、みんなで支え合う地域づくりにつなげていきます。 (1) 地域文化事業の実施(嬉野台、但馬、西播磨、淡路) 従来から取り組んできた各地域の伝統芸能、音楽、文芸、美術、スポーツ等地域文化の振興を図る発表会、コンサート、公募展、イベント開催等について、引き続き地域の関係団体、住民の参画と協働により事業を継続していきます。 [地域文化活動の振興] 事業名 事業概要 主な実施団体 ①嬉野台生涯教育センター ア うれしの春のフェスティバル 施設開放を行い、芸術、文化、スポーツ、地域活動団体の交流などを通じて、家族間、世代間、地域間の交流の促進を図るとともに、利用者の拡大を図る。 実 施 日:令和2年5月4日(月) 参加者数:約4,000人 うれしの春のフェスティバル実行委員会 イ うれしのまるごとギャラリー 年間を通じて絵画、写真、書、木彫、陶芸、染色等を展示することで作品発表と鑑賞の場を提供します。 実 施 日:通年 出 展 数:約200点 センター自主事業 ウ 東はりま大茶会 茶道文化の交流事業を実施し、伝統文化の保存・継承を図るとともに地域文化の振興と普及拡大を図る。 実 施 日:令和2年10月4日(日) 参加者数:約630人 東播磨文化団体連合会、東はりま大茶会実行委員会 エ 東はりま芸能祭 芸術活動を進める団体に発表の場と交流の機会を提供し、団体の育成を図るとともに、広く県民に鑑賞の場を設けることで伝統芸能の啓発普及を図る。 実 施 日:令和2年10月18日(日) 参加者数:約500人 東播磨文化団体連合会、東はりま芸能祭実行委員会 オ 東はりま 合唱団体による発表と交流の場を提供し、音楽団体の育成を図るとともに、個性ある文化活動の向上を図る。 実 施 日:令和2年10月25日(日) 参加者数:約500人 東播磨文化団体連合会、東はりまコーラス大会実行委員会 カ 東播磨選抜美術展 公募による美術展を開催し、優れた作品にふれる機会を設けるとともに、創作意欲を喚起することにより東・北播磨地域における美術の振興を図る。 実 施 日:令和3年2月26日(金) 参加者数:約500人 東播磨文化団体連合会、東播磨選抜美術展実行委員会 キ 東播磨の地域文化を考える会 東播磨・北播磨地域各市町文化協会・団体の会員等が一堂に会し、地域における文化振興の現状や課題、地域の特色を生かした事業の推進方策等について情報交換や協議を行う機会とします。 実 施 日:令和3年3月6日(土) 参加者数:約200人 東播磨文化団体連合会 ク 東はりま みんように取り組む団体の発表と交流を通して、伝統芸能の継承を図ることにより地域文化の活性化を図る。 実 施 日:令和3年3月28日(日) 参加者数:約500人 東播磨文化団体連合会、東はりまみんよう大会実行委員会 ケ 文芸誌「東はりま文化子午線」の発行 東播磨・北播磨地域の県民を対象に公募した短歌・俳句・川柳・詩・随筆等の作品を中心とした文芸誌の発行を通して、文化活動の裾野の拡大と地域文化の活性化を図る。 発 行 日:令和3年3月31日(水) 発行部数:1500部 東播磨文化団体連合会、東はりま文化子午線発行委員会 ②但馬文教府 ア 文教府夏期大学 県民の教養を高め、こころ豊かに暮らすため、斯界の第一人者を招き講演会を開催し、但馬地域の文化、教育の振興を図る。 実 施 日:令和2年8月22日(土) 実施場所:豊岡市民会館文化ホール 参加者数:約1,000人 但馬文教府夏期大学実行委員会 イ 但馬美術展 日本画・油彩画・水彩画・版画・ミクストメディアの5部門からなる公募展を実施、鑑賞の場を提供することにより美術の発展を図る。 実施期間:令和2年7月31日(金) 芸術文化振興事業実行委員会 ウ ふるさとの心をうたう但馬合唱祭 但馬各地の合唱団体が一堂に会し、日頃の練習成果の発表と交流によりふるさと但馬の文化振興を図る。 実 施 日:令和2年11月23日(月・祝) 参加者数:約1,000人・約40団体 芸術文化振興事業実行委員会 エ 但馬歴史講演会 但馬史へ理解を深め郷土愛を育むため、但馬の歴史や遺跡等についての講演会を実施します。 実施日:令和2年11月 芸術文化振興事業実行委員会 オ 但馬文学のつどい「たじま作品集」の発行 短歌、俳句、冠句、川柳の合同作品展と研さん交流の会を開催するとともに、但馬在住者及び但馬のグループに所属する人を対象に短歌・俳句・冠句・川柳、詩を募集し、短詩型文学『たじま作品集』として発行します。 実施日:令和2年11月14日(土) たじま作品集の発行日:令和3年3月 但馬文学のつどい企画運営委員会 カ 但馬ふるさと 芸術文化祭 但馬で芸術・芸能活動に取り組む個人や団体、学校などが日頃の成果を発表し、ふるさと但馬の芸術・文化のさらなる振興を目指す。 実施日:令和2年10月1日(木)~4日(日) 但馬ふるさと芸術文化祭実行委員会 ③西播磨文化会館 ア 播州段文音頭大会 地域に唄い継がれてきた播州段文音頭の保存会を支援するため、交流の機会を提供することで、活動の活性化とともに、地域文化の振興を図る。 実 施 日:令和2年8月29日(土) 参加者数:約300人 播州段文音頭大会実行委員会 イ 播州段文音頭教室【新規】 播州段文音頭の担い手を養成するため、各市町文化協会や保存会と連携し、音頭及び太鼓を学ぶ機会を設ける。 実施日 隔週月曜 参加人数 各回40人程度 播州段文音頭大会実行委員会 ウ ふるさとの心をうたう西播磨音楽祭 中播磨・西播磨各地で活動している合唱団等の音楽活動団体に発表と交流の場を提供し、それら団体の育成を図るとともに、中播磨・西播磨の特色ある芸術文化活動の向上を図る。 実 施 日:令和2年12月6日(日) 実施会場:山崎文化会館 参加者数:約400人・15団体 西播磨ふるさと芸術文化振興事業実行委員会 エ 西播磨ふるさと写真展 作品を通し、明日の西播磨を考える機会を提供するとともに、作品の鑑賞を通して、互いの技量の向上や交流の輪の拡大を目指し、地域文化の活性化を図る。 テ ー マ:中・西播磨の自然と文化 募集期間:令和2年7月1日(水) 表 彰 式:令和2年9月5日(土) 西播磨ふるさと芸術文化振興事業実行委員会 オ 西播磨短歌祭 中播磨・西播磨地域の短歌愛好者の作品を公募し、入選者を表彰するとともに、講師を囲んで作品の鑑賞を行う中で、互いの交流と創作意欲の高揚を図る。 募集期間:令和2年7月1日(水) 実 施 日:令和2年10月31日(日) 西播磨ふるさと芸術文化振興事業実行委員会 カ 西播磨俳句祭 中播磨・西播磨地域の俳句の愛好者の作品を公募し、入選者を表彰するとともに、講師を囲んで作品の鑑賞を行う中で、互いの交流と創作意欲の高揚を図る。 募集期間:令和2年7月1日(水) 実 施 日:令和2年10月24日(土)) 西播磨ふるさと芸術文化振興事業実行委員会 ④淡路文化会館 ア 淡路人形浄瑠璃後継者交流発表会 淡路人形浄瑠璃に影響を受けた全国の人形浄瑠璃後継者団体等と連携し、後継者の交流と発表の機会をつくるとともに、各団体のネットワーク化と全国への情報発信を推進する。 実施日:令和2年7月25日(土)~26日(日) 会 場:洲本市文化体育館 出演者:島内外後継者団体(中・高校等) 淡路人形浄瑠璃後継者交流発表会実行委員会 イ 淡路島ココだけの音楽祭(仮称)【新規】 淡路地域で保存・継承されている伝統芸能や民俗芸能、淡路島をテーマとした創作芸能や様々な音楽に取り組む団体が一堂に会し、お互いの舞台発表等を通して交流することで、地域文化の振興を図る。 実施日:令和2年12月20日(日)(予定) 会 場:淡路市立しづかホール 淡路島ココだけの音楽祭実行委員会(仮称) ウ 淡路日本画 日本画の創作技術の習得と鑑賞眼を養うとともに、芸術に親しむ心を培う機会を提供する。 初級、中級の2コースに分けて開催 年間10回 定員:初級30名、中級20名 兵庫県立淡路文化会館運営協議会 エ 淡路洋画 洋画の創作技術の習得と鑑賞眼を養うとともに、芸術に親しむ心を培う機会を提供する。 年間10回 定員:50名 兵庫県立淡路文化会館運営協議会 オ スプリング 淡路島内の音楽関係団体や愛好家に発表と交流の機会を提供し、淡路地域の声楽芸術文化活動の向上及び裾野の拡大に努める。 実施日:令和3年3月7日(日)(予定) 会 場:淡路市立サンシャインホール 兵庫県立淡路文化会館運営協議会 カ 第39回 短歌作品を募集し、優秀作品を表彰することで、淡路地域の短歌愛好家の交流と創作意欲の高揚を図る。 実 施 日:令和2年7月中旬 淡路文化団体連絡協議会 キ 第44回 俳句作品を募集し、優秀作品を表彰することで、淡路地域の俳句愛好家の交流と創作意欲の高揚を図る。 実 施 日:令和2年11月中旬 淡路文化団体連絡協議会 ク 第42回 作者自ら書写した短歌・俳句・雑排を展示することで、淡路における短詩型文学の振興を図る。 実 施 日:令和2年11月下旬~12月上旬 淡路文化団体連絡協議会 (2) 文化会館等の特性を生かした利用促進
文化会館等は、地域の特色ある文化活動の拠点として市域を越えた地域文化団体の事務局を担うなど、伝統文化の伝承活動、住民のふるさと意識の醸成、広域交流のたまり場としての役割などを担っています。 ①地域文化活動の支援 支援団体等 支援内容 ①嬉野台生涯教育センター ア 東播磨文化団体連合会への支援 東播磨・北播磨地域内の各種文化団体の連携と研修を深め、地域の芸術文化の高揚を図ることを目的として設立された東播磨文化団体連合会が実施する各種事業や活動等を支援 ②但馬文教府 ア 但馬文化協会への支援 但馬地域住民の文化に対する関心を高め、郷土文化の振興を目的として設立された但馬文化協会が実施する各種事業や活動等を支援 イ 但馬芸術文化会議への支援 但馬地域住民の芸術・文化活動の振興を目的として設立された但馬芸術文化会議が取り組む各種事業や活動等を支援 ウ 但馬美術協会への支援 但馬地域の美術(絵画)振興を図り、郷土文化の向上に寄与することを目的として設立された但馬美術協会の事業、活動等を支援 エ 但馬市郡婦人会連絡協議会への支援 但馬各市町地域婦人会相互の連絡を密にし、但馬のくらしと文化の促進を図り、婦人の資質向上と地域の発展を目指すことを目的として設立された但馬市郡婦人会連絡協議会の各種事業、活動等を支援 ③西播磨文化会館 ア 西播磨文化協会連絡協議会への支援 中播磨・西播磨地域住民の文化に対する関心を高め、郷土文化の振興を目的として設立された西播磨文化協会連絡協議会が取り組む各種事業や活動等を支援 ④淡路文化会館 ア 淡路文化団体連絡協議会への支援 淡路地域住民の文化に対する関心を高め、郷土文化の振興を目的とした設立された淡路文化団体連絡協議会が実施する各種事業や活動等を支援 ② 文化会館等活性化事業 令和元年度で3年間の最終年度を迎えていた各文化会館等での一層のにぎわいの獲得を目的とする各文化会館等活性化事業の継続により、生涯学習・地域づくり活動のより一層の活性化を図ります。 活性化事業 嬉野台生涯教育センター ア 北播磨人(きたはりまびと)意識醸成事業【再掲】 但馬文教府 ア 但馬ふるさと芸術文化祭【再計】 イ 科学チャレンジin但馬文教府【再掲】 西播磨文化会館 ア 子どもも大人も楽しめる「文化体験教室」【再掲】 子どもから高齢者まで参加できるように、生活創造グループ、地域団体、高齢者大学生、地元高校生等が参加して展示・出店・発表等を行う等、大規模イベントを開催します。 ウ ゆうゆうの森音楽フェスティバル 音楽会を定期的に開催し、中・西播磨地域の音楽文化の振興を図る。また、施設を音楽の会場・練習場として利用促進につなげていきます。 エ 播磨「歴史・地域学」講座&フォーラム 中・西播磨地域の歴史・文化・産業などを学ぶ講座&交流フォーラムを山城をテーマに実施するとともに、地元への愛着、ふるさと意識の向上に寄与します。(年4回を予定) 淡路文化会館 ア 国生みの島元気っ子フェスティバル【再掲】 イ 夏休みサイエンス体験広場【再掲】 小学生・中学生・高校生及びその保護者の会館利用を促進するため、児童・生徒向け課外学習教室を開催します。(例:スポーツウエルネス吹き矢、絵手紙等) オ 文化・教養・スポーツに関する入門講座 様々な分野の生涯学習に取り組むきっかけとしてもらうために、文化・教養・スポーツなどの入門講座を開催します。 カ 生活創造活動グループ交流会【再掲】 6 文化・芸術活動の拠点としての機能強化 (1) 但馬文教府「ふるさと交流館」の開館【新規】 老朽化した活動体験館を建替え、新たに多目的に活用できるホールを備えたふるさと交流館を整備して但馬地域の文化・芸術活動の拠点として機能強化を図ります。 7 経営の健全性・透明性の確保 今後とも、県民の主体的な学びを先導する生涯学習事業を、県民の信頼を得ながら、安定的、持続的に進めていくため、引き続き選択と集中の徹底、コスト削減に取り組むとともに、安定財源の確保を図るなど、経営の健全性・透明性の確保に努めていきます。 (1) 自主財源等安定した収入の確保
① 高齢者大学入学者の確保 応募者数が減少傾向にあることから、魅力的なカリキュラムの設定、施設の改修など、高齢者大学の魅力向上を図り、入学者定員の確保に努めます。 特に、令和2年度は、いなみ野学園の運営について、検討の場を設けて、見直しの検討を行います。 また、入学者募集の際に効果的な口コミによる周知を図るため、学生・卒業生等への高齢者大学に関する定期的な情報提供を行うほか、PR効果の高いホームページ、マスメディアの活用など、効果的なPRに努め、認知度の向上を図ります。 ② 適正な受益者負担の徴収 ・協会事業に係る経費について、適正な受益者負担を求めていきます。 ③ 寄付募集の推進 いなみ野学園創立50周年を機に、令和元年度から寄付募集を開始しました。今後も寄付の推進を図ります。 ④ オープンキャンパスの開催(いなみ野、阪神、嬉野、但馬、西播磨、淡路) 施設の見学を通じて入学志望を高めてもらうため、オープンキャンパスを開催します。 ⑤ 自主事業の収益の確保 経営手法の見直しや送迎バスなど利用者の利便性向上を図り、利用者の増加に努めるとともに、いなみ野学園の学生・卒業生等との連携により、農産物の栽培体制の整備を図り、販売拡大を目指します。 ア 高齢者手づくりの店(協会本部) 高齢者が、趣味、創作活動として製作した手工芸品や民芸品、育成した野菜・花などを販売する場として、引き続き、民間事業者に委託して運営します。 ・出品物 野菜、花き、果物、苗、菓子、手芸品など ・施設の概要 木造平屋建寄棟造 117.9㎡ イ 高齢者園芸センター(協会本部) 高齢者が土と親しみ作物を育てることを通じて健康を増進するとともに、地域や世代間の心のふれあいと交流を図る場として運営します。 (ア) 指導者付貸農園(ファミリーファーム)の運営 ・区画数 448区画(16.5㎡;395区画、30㎡;14区画、32㎡;39区画) ・利用料 16.5㎡ 7,200円/年 (イ) 施設の概要 ・ファミリーファーム 11,620㎡ ・農 園 4,415㎡ ・果樹園 6,330㎡ ・管理棟 176㎡ ウ 高齢者陶芸の村(協会本部) 高齢者が作陶活動を通じて、仲間と共に生きがいを創造する場として、会員の自主運営により実施しています。 (ア) 会員の入村・利用料等 ・会 員 60歳以上の者 ・入村料 12,000円 ・利用料 月額3,500円(3月分前納) ・材料費・焼成費 粘土10㎏につき2,300円 ・作陶日:週2回(月・火と木・金の2班) 指導員が作陶焼成等の指導にあたります。 (イ)地域への開放 地域の人々に施設を開放し、広く陶芸の普及と世代間交流を図ります。 ・利用料 一人1日500円 ・材料費・焼成費 粘土1㎏につき530円 ・指導員が作陶焼成等の指導にあたります。 ・作陶日:毎週水曜日 (ウ) 施設の概要 ・敷地 2,820㎡、建物 720.78㎡ ・作業棟3棟451.11㎡、窯棟3棟120.43㎡、乾燥棟72㎡、その他78.24㎡ (2) 施設の改修による利便性等の向上 各施設の状況、所要経費等を勘案し、利用者の利便性・快適性を確保して利用者増を図るための施設改修を計画的に進めます。 (3) 職員の適正配置等による運営 長期的視点で事業を計画的、継続的に執行することができるよう職員の適正配置等による運営を行うとともに、高齢者大学のクラス運営等のルーティン業務を運営サポーター等による自立的運営に移行するなど、高齢者が高齢者を支援する体制で運営を行います。 (4) 協会事業の透明性確保・広報の充実
① 協会事業の見える化 ア 協会ホームページで、組織・収支状況・経営方針・事業内容・イベント情報などを定期的に発信します。 イ ニュースレター「生きがい通信」(協会本部)
高齢者の生きがいと健康づくりに関する情報などをニュースレターとしてホー ムページに掲載することにより、地域社会への貢献についての県民の意識啓発を図るとともに協会事業の内容を積極的に発信します。 ・発信回数 年3回 ② マスメディアとの連携 ラジオや新聞等のマスメディアの協力を得ながら、当協会及び協会事業の知名度向上、地域づくり活動の場の確保を図っていきます。 ア 記者発表等マスメディアの積極的活用の推進 イ ラジオ関西との共同制作番組「いなみ野シニアの元気ニュース」 ③ いなみ野学園情報提供番組の制作・発信(いなみ野) 地域ケーブルテレビ局「BAN-BANテレビ」の協力を得て、大学院講座学生等の自主制作により放映している番組「いなみ野学園情報」への応援を通じて、学園行事等の情報発信に努める。 ④ ホームページの運営(全施設) 可能な限りの情報公開を目指すとともに、わかりやすく、親しみやすい、身近に感じてもらえる施設像の情報発信に努めていきます。
学生等による地域活動の実践に助言を行います。
学生等による地域活動に係る情報提供作業を行います。
(8名)
〔採用対象〕研究生
〔採用対象〕研究生
(30名程度)
・活動日数 年4回
・内 容 野菜等生産物の販売
毎日の授業時間数=90分の講義、実習と園外実習
実習費(年間) 園芸学科のみ3,000円
○地域の魅力や課題を探り、解決を図る能動的な地域活動の分野
○人間関係、コミュニケーション、心理学の分野
・歴史や文化、言語、経済、自然、都市の活力、高齢化など阪神地域の魅力や課題
・傾聴力、発想法、リーダーシップなどの観点から、協力・協調する力を養成
○オーガニックで、五感で楽しむ五つの実習園
○家庭園芸家から農家をめざす方まで、カレッジ職員が個別サポート
・野菜や花、ハーブや果樹などをオーガニックな手法で実習
・講座で聞けなかった農家の知恵やベランダ園芸のテクニックを個別にサポート
○健康阻害要因についての知識
○健康長寿を実現する実践的知識
・環境、大気、排出ガス、化学物質、アレルギー、土壌、バイオテクノロジー等を考察
・薬害、代謝、アルコール体質、食、栄養、遺伝子、睡眠、伝統医学等を学習
○グローバリゼーションの現状と課題
○国際協力・地域国際化
○校外学習
・日々の暮らしが、地域社会が、国家が世界と密接に繋がり影響を受けていることを学習
・JICA関西への訪問研修など日本における難民問題や外国人労働者問題を学習
・「ほんもの」に触れる機会を提供し、文化の多様性を学ぶきっかけづくりを実施
授業日数 年間30日
○地域を知る
○地域活動の理解を深める
○グループ活動
開講日 原則として月2回隔週火曜日
(総合講座)
開 講 日 原則として月2回隔週火曜日
活動の内容や成果を冊子にまとめ、実践発表を行います。
開講日 原則として月2回隔週金曜日
(教養講座)
・今日的課題に関する講座4回
・文教府夏期大学1回
・高齢者の病気、食生活、医療や介護などについて学ぶ。
(靴と足の科学、音楽と健康、骨粗鬆症、生活習慣病等)
(香住の三番そう、川下祭りと麒麟獅子、出石のお城まつり 等)
(但馬牛の歴史・特徴、但馬の杜氏と酒祭り、但馬の漁業 等)
・ボランティア活動や社会福祉、子育て、地域づくりについて学ぶ。
・ワークショップの手法やパソコンの基本的な操作について学ぶ。
実践講座
・但馬地域にある地域活動の資源を探る。
・豊岡短期大学と連携し、豊岡短期大学の学園祭でも実践発表します。
・グループ別活動に向けた取組をすすめる。
・グループ別実践活動のテーマをもとに学ぶ。
実践講座
・実践活動発表会で内容や成果を発表するとともに、研究冊子にまとめる。
開 講 日 原則として月2回隔週金曜日
コース
※左の3コースから1コース選択
コース
コース
地域活動に意欲のある概ね60歳以上の者
開 講 日 原則として月2回隔週木曜日
地域活動に関する実践事例や企画運営の手法等を学ぶ。
専門コース(環境創造・健康福祉・地域文化)ごとに調査、研究、実践活動を行います。
2年間の成果を修了レポートとしてまとめ、報告会で発表します。
開講日 原則として月2回隔週水曜日
(教養講座)
コース
生活実践力を育成します。
※1コース選択
コース
・防災学習、環境学習、地場産業体験
1年「仲間と共に」
2年「淡路を知ろう」
3年「地域交流と実践」
4年「学びを生かして(成果発表)」
淡路島ココだけの音楽祭(仮称) 等
開 講 日 原則として月2回隔週金曜日
地域づくり活動に必要な基礎的知識を幅広く身につけるとともに、実践者から現状や成果、課題等を聞き、総合的、体系的に企画運営の手法を学びます。
・課題演習
地域づくり活動に向けて、ものづくりや健康・環境又は歴史、文化等の専門的知識やノウハウを身につけます。
・事例研究
淡路島の特色について、地域の郷土史家や伝統芸能後継者等との交流をとおして、地域の特色について学ぶとともに淡路島の「よさ」を再発見します。
地域づくり活動への主体的な取り組み意欲を醸成するとともに、専門的に学びを深めていきます。
・実践演習
受講者が自らテーマを決め、主体的に調査活動等を行い、地域の特色や淡路島の「よさ」について論文にまとめていきます。
・実践活動
地域イベント等において、世代間交流を積極的に推進する等、地域づくり活動に向けての可能性を探ります。
さらに、「仕事をしながら学べる」「自宅に居ながら学べる」特長を発信し、多世代が興味・関心を持つ分野を積極的に学習内容に取り入れていきます。
聴講生:居住地、年齢等不問
生涯聴講生:原則として本科を修了した者
※テキスト購読料を含む年額
各友の会はお互いに交流を図りながら、学習会やボランティア活動などを自主的に実施しています。
(学習内容)
①健康・医療
②文化・歴史
③生きがいづくり
④政治・経済、自然科学、地域づくり、その他社会的話題性を有する事項
いなみ野学園キャンパス
阪神・神戸、丹波、但馬、
西播磨、東播磨、淡路の各地域
いなみ野学園キャンパス
(協会本部、いなみ野、放送大、阪神、嬉野台、但馬、西播磨、淡路)
また、参加者の年齢や体験グループの成熟度、活動内容(体験時間等)等に応じた適切なアレンジによりHAP体験の機会を提供します。
さらに教育関係者やHAPに携わる指導者等のセミナー及び講習会を実施し、指導者等の資質向上を図るとともに、出前講座として学校や団体へ出張し、新たな指導者育成を行います。
(教育実習生を「うれしの台ユースセミナー」におけるリーダーとします。)
また、ゆうゆう学園生がSP(模擬患者)となり、高校生が継続的な看護ケアを行う看護科実習ボランティアに取り組んでいきます。
なお、令和2年度は、同窓会設立20周年に当たることから、その周年事業についても連携を図っていきます。
また、ゆうゆう学園クラブや同好会が、西播磨県民局主催の「西播磨フロンティア祭」で開催される「出る杭大会」に出場し、日頃の地域づくり活動を発表することで更なる地域づくり活動の活発化を図っていきます。
・「親子陶芸教室」の継続実施
コーラス大会
~28日(日)
みんよう大会
~8月7日(金)
~31日(金)
~9月10日(木)
~8月25日(水)
セミナー
セミナー
コンサート
全淡短歌祭
淡路島俳句大会
淡路文学作品展
今後も広域地域文化拠点として、日常的、継続的な賑わいを創出するため、地域の文化団体、地域団体、生活創造活動グループ、高齢者大学学生・卒業生で構成する団体、NPO等の参画と協働による活性化事業を実施し、利用促進を図っていきます。
<支援内容>
地域文化団体との連携調整をはじめ、「東播磨の地域文化を考える会」の開催や文芸誌「東はりま文化子午線」の発行など
〈支援内容〉
地域文化団体との連絡調整をはじめ、但馬文化協会機関紙「KOHNOTORI」発行、ふるさと芸術文化振興事業等
〈支援内容〉
地域文化団体との連絡調整をはじめ、「但馬ふるさと芸術文化祭」開催運営支援、但馬文化賞・青少年文化奨励賞の実施、機関紙「芸文たじま」の発刊など
〈支援内容〉
地域文化団体との連絡調整をはじめ、但馬美術展の開催、但馬美術協会報の発行など
〈支援内容〉
地域文化団体との連携調整をはじめ、但馬市郡婦人会交流会、但馬文教府と共催で実施する研修会など
〈支援内容〉
地域文化団体との連絡調整をはじめ、子どもも大人も楽しめる「文化体験教室」、西播磨地域ふれあい文化交流会、新年文化交流会の開催、機関誌「西播磨文化」の発行など
〈支援内容〉
地域文化団体との連絡調整をはじめ、ふるさと文化交流事業の開催や機関誌「あわじ」の発行等
![]() 施設名
施設名
イ 北播磨地域ふれあい事業(仮称)【再掲】
ウ 多世代ふれあい交流次号【拡充】【再掲】
エ 文教府ジュニア陸上教室【再掲】
イ 西播磨ふるさと文化祭
・実施日 令和2年11月29日(日)
西播磨で人気の高いオカリナについて、オカリナ製作体験、プロに学ぶオカリナ教室等を実施します。
ウ 地域公開講座【再掲】
エ 児童・生徒向け課外学習教室【新規】
キ 文化情報提供事業(淡路文化会館ライブラリー)【再掲】
また、竣工を記念して、開館記念式典やオープニングイベントを開催します。
特に、令和2年度にあっては、高齢者大学の学園生負担金が減少してきており、財務運営が大変厳しい状況になってきていることから、令和2年度当初から取り組むことが可能な事務事業については、収支予算に反映しているところです。その他の事業についても、収支改善に有効な事務事業については、可能な限り、見直しを行っていきます。
また、令和元年に採択された「ふるさとひょうご寄附金」(使途は「いなみ野学園多世代交流応援プロジェクト事業」限定)についても、ホームページ等を通じて県外在住者などへの周知に努め、寄付受納の一層の促進を図ります。
講義参観やクラブ見学のほか、秋の「文化祭」開催時には地域内の住民に広く参加を呼びかけるなど一般県民に開放することで、高齢者大学での学びや活動への理解と啓発を図り、生涯学習を推進する機会とします。
シニアによるシニアのための情報提供ラジオ番組については、学園生による企画・取材・出演という制作方法を基本としつつも、他の高齢者大学生の参画を得た広範なシニア向け情報番組とし、生涯学習への意欲喚起に努めます。